
フランスが舞台となっている作品は映画、小説、絵画・・・などなど、多数存在します。
ミュージカル作品においても同様に、フランスが舞台となっている人気作品はたくさんあるのです!
作中でフランスを含めたヨーロッパを跨いだストーリー展開する作品もありますが、今回はフランス国内にどっしり腰を据えて物語が進む作品8選をご紹介します。
もくじ
①『レ・ミゼラブル』
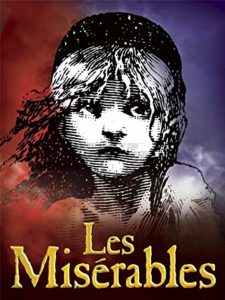
脚本・監督・音楽
原作:ヴィクトル・ユゴー
脚本:クロード=ミシェル・シェーンベルク
音楽:クロード=ミシェル・シェーンベルク
あらすじ
舞台は19世紀フランス。
19年間投獄されていたジャン・バルジャンは仮出獄を言い渡される。しかし罪人であるが故の世間の冷たさに打ちひしがれ、心が荒んでいくバルジャン。
寝る場所すらなく彷徨っていたところを教会の司教に助けられるも、人を信じられなくなっていたバルジャンは銀の食器を盗んで逃げようとする。
しかし逃げる道中に市民たちに見つかり、暴行を受けるバルジャンと駆けつける司教。そこで司教はバルジャンにこう言い放つ。
お急ぎなされてどうしたのです。とっておきのもの(2つの燭台)をお渡しそびれるところでしたよ。
司教の慈悲に触れ、頭を殴られたような衝撃を受けるバルジャン。ここから彼の贖罪の人生が始まった。
みどころ
ジャン・バルジャンの贖罪の人生を追っていく作品。
その中で彼が出会ったタイトル通りの”哀れな人々”のそれぞれの生き様を激動の19世紀フランスの中でまざまざと見せつけられます。
「ミュージカルの金字塔」と呼ばれるだけあって、老若男女誰が見ても心打ち震える名作。
音楽・ストーリー・演出、そのどれをとっても1点の減点の余地もないほどの作品です。日本では2年おきに全国ツアーを実施しているので、最近ミュージカルに興味を持ったという人はぜひ次回の2021年公演をチェックしてほしい!
やはりミュージカルというエンターテインメントは少し女性向けに作られていると思います。しかし、この『レ・ミゼラブル』だけは男性が観ても絶対に感動できると自信を持ってオススメできます。
『レ・ミゼラブル』って『CATS』みたいに劇場全体に仕掛けがあるわけでもなければ、『オペラ座の怪人』のように豪華な装飾や衣装を楽しめるわけでもない。
正直、ミュージカルの中ではビックタイトルの割には舞台装飾は地味なほうだと思います。
ミュージカル作品において舞台芸術ってかなり重要な要素なので、結構なディスアドバンテージであるはずなんですよ。でもそんなものを跳ね除ける程、とにかくストーリーが素晴らしいです。本当に最高のストーリー。
『レ・ミゼラブル』を見てもなんの感動もしなかった人。アナタ、きっと人間ではありません。自分がアンドロイドだと気づいていない高性能アンドロイドの可能性が高いです。
いきなりミュージカルはちょっと敷居が高いなぁ・・・という人にはまず映画版を見てみることを推奨します!
②『ノートルダムの鐘』(劇団四季)

脚本・監督・音楽
原作:ヴィクトル・ユゴー
脚本:ピーター・パーネル
演出:スコット・シュワルツ
音楽:アラン・メンケン
あらすじ
舞台は15世紀末のパリ。
街の中心にそびえたつノートルダム大聖堂。そこにはカジモドという鐘付きが住んでいた。
生まれつき背骨が大きく湾曲している”せむし男”のカジモド。その容姿から、大聖堂の中になかば監禁のような生活を強いられていた。
楽しみといえば塔の上からパリの街を眺めること。そんなカジモドに対して初めて優しく接した美しい踊り子のエスメルダ。カジモドはいつしか彼女に愛を抱くようになる。
しかし、聖職者であるフロローは邪念と理解しつつもエスメラルダの魅力に惹かれていく。堕落へ導く彼女を街から追い出そうと、フロローは彼女を排除しようとするが・・・
みどころ
なんといってもフランスが誇る文豪ヴィクトル・ユゴーとディズニー音楽の神アラン・メンケン、この2人が織りなす作品ということでしょう!
ホント、異種格闘技戦みたいな組み合わせだと思います。
劇団四季の作品といえば『ライオンキング』や『キャッツ』など比較的明るくて楽しい作品が多いイメージがあるかもしれませんが、この作品はかなり異色。
原作のディズニー映画版よりもさらに深く、濃く、鋭い作風になっています。人間が持つ闇とか、罪とか、そういったものにスポットライトを当てている作品なんですよね。
ディズニー?劇団四季?女子供向けだろォ??
というお父さんも心撃たれること間違いなし。
そして、この作品の裏主人公はフロローだと筆者は思っています。
彼はディズニー作品の歴代ヴィラン(悪役)とは一線を画すポイントがあるんです。それは自分こそ正義だと信じていること。
ディズニーの悪役って、「自分は悪人だ」「悪事を働いている」と自覚していることがほとんどなんですよ。でもフロローだけは自分の行いになんの疑問も抱かず、ひたすら正義だと信じ込んでいる。
そんな実直な男がエスメラルダに出会って、自身の正義とか純潔が足元からグラグラと崩れ落ちていく。
幼い子供がこの作品を観たら間違いなくフロローは悪役だし、セクシーなヴィランが多いディズニーとは思えないほど鳥肌モノの気持ち悪さを誇る異色の存在。
確かに悪であることは間違いないし残忍でどうしようもない男なんですが、彼は彼なりの正義を突き通そうとしただけなんだよな・・・という見方をしてみると、また違った発見があるはずです。
③『美女と野獣』

脚本・監督・音楽
脚本:リンダ・ウールヴァートン
演出:ロバート・ジェス・ロス
音楽:アラン・メンケン
あらすじ
フランスの片田舎で研究家の父を2人暮らしのベル。
夢と冒険の世界に憧れ、本ばかり読んでいる彼女は小さな村では変わり者。
一方、美しい王子であったが傲慢な性格ゆえ、獣の姿に変えられてしまったビースト。彼が人間の姿に戻る条件は「愛し、愛されること」
ある日、父が帰ってことないことに異変を感じたベルは父を捜しに行きますが、森の奥深くにある城に迷い込んでしまう。そこでは父がビーストによって囚われていたのだ。
父を助ける代わりに身代わりとなって城に残ることを決意するベルであったが・・・
みどころ
2017年にエマ・ワトソン主演で実写映画化され、ミュージカル映画の火付け役となりましたよね。
映画版ではとにかく美しい映像美が話題となりましたが、ミュージカル版ではディズニーミュージカルらしい躍動感溢れる作風になっています。
今でこそ、「自立した強い意思を持ったヒロイン」はさほど珍しくありませんが、ディズニー版の公開当時の1991年では良い意味でディズニーのヒロインらしくないヒロインであったベル。
映画版よりもミュージカル版のほうが知性と冒険心の溢れるベルらしさを感じられると筆者は思っています。
④『オペラ座の怪人』

脚本・監督・音楽
原作:ガストン・ルルー
脚本:アンドリュー・ロイド・ウェーバー
音楽:アンドリュー・ロイド・ウェーバー
あらすじ
舞台は19世紀パリ。
オペラ座では舞台「ハンニバル」のリハーサルが行われていた。しかし、オペラ座に棲みつく”オペラ座の怪人”によって次々と怪奇な現象が起きていた。
怪人の仕業に対して対策を打とうとしない支配人に対してオペラ座のプリマドンナであるカルロッタは舞台を降りてしまう。
そこで彼女の穴を埋めるべく抜擢されたのがクリスティーヌ・ダーエであった。
彼女は亡き父の贈り物である”音楽の天使”たちによるレッスンによって磨かれた類まれな美しい歌声を披露し、一躍スターとなる。
しかし、彼女に”音楽の天使”を使って夜ごと歌を教えていたのは、怪人の仕業であった・・・
みどころ
世界3大ミュージカル『キャッツ』、『レ・ミゼラブル』、そしてもう一つがこの『オペラ座の怪人』!
ミュージカルといえばこの作品を第一にあげる人も多いんじゃないでしょうか。世界で最も愛されたミュージカルと呼ばれるほど世界中で人気のある作品です。
「オペラ座の怪人ってよく聞くけど、何がそんなにいいの?」
と疑問に思う人もいるかもしれません。
たしかに悲恋を描いた作品はたくさんあるし、良質な楽曲が目白押しの作品もそりゃもう大量にある。
でもなぜオペラ座の怪人はそこまで素晴らしいのか?というと、舞台装飾が完璧であることが世界一愛されるミュージカルたるゆえんなのだと思います。
舞台装飾がすごいミュージカルはもちろんたくさんあるけど、オペラ座の怪人はちょっと群を抜いているんですよね。
美しさ、迫力、緻密さ・・・次から次へと様変わりするミステリアスで豪華な世界。これ、CGを使った映画のワンシーンじゃないの?と錯覚するようなシーンだらけです。
とにかく装飾ひとつひとつがどれをとっても緻密なんですよね!
デザインだけでなく質感とか使い込まれてる感とか、まさに神は細部に宿る。
⑤『マリー・アントワネット』

脚本・監督・音楽
原作:遠藤周作『王妃マリー・アントワネット』
脚本:ミヒャエル・クンツェ
演出:ロバート・ヨハンソン
音楽:シルヴェスター・リーヴァイ
あらすじ
舞台は18世紀末フランス。
オーストリアから嫁いできたフランス王妃マリー・アントワネットは愛する子供たち、豪華なドレス、従順な家来たちに囲まれて幸せの絶頂であった。
しかし一方、明日生きていくためのパンすら手に入らないほどパリは貧困にあえいでいた。マルグリッド・アルノ―もその一人であった。
国民に目を向けず贅沢三昧の王政を打倒せよ!パリの市民たちは革命に燃えていた。
市民たちの憎悪の対象となったのはオーストリア人であるにも関わらずフランス財政を貧窮に陥れるほど贅沢したマリー・アントワネットであった。
革命の渦に巻き込まれていくアントワネットと、マルグリッド。2人のM・Aが織りなす物語。
みどころ
フランス革命ミュージカルといえば今作でなくとも多数ありますが、その中でも美しさという点においてずば抜けた作品です。
見どころといえば、なんといっても豪華絢爛な舞台装飾と衣装・・・
と言いたいのですが、この作品の真のみどころは王妃マリー・アントワネットを1人の女性としてリアルに描いていることだと思います。
アントワネットが登場する作品はミュージカルに限らず人気がありますが、そのほとんどは美しく気高いフランス王妃としての姿を描写しています。
そのため、一人の女性というよりはフランスの美しいロココ文化の象徴のような存在として登場していることが多いんですよね。
しかし、ミュージカル『マリー・アントワネット』は王妃としてではなく一人の女性、母、恋する乙女として生生しく彼女を描いています。
例えば、アントワネットは処刑されて人生に幕を降ろしますが、処刑に向かうアントワネットを気高く美しく描いた作品がほとんどです。『ベルサイユのばら』なんて少女漫画らしく最期の瞬間まで麗しく描かれています。
しかしこのミュージカルでは幽閉から処刑までのアントワネットは焦燥しきり、まるで死人のように何の光も映さない瞳。それでも最期の瞬間まで王妃たる堂々とした姿を見せます。
ラストシーンに近づくにつれ、限界まで消耗しきっている様子がかなり生生しいんですよ。ゾっとする恐怖すら感じます。
一見するとキラキラした作品に見えがちですが、実はかなりリアルで残酷。美しい装飾やドレスに隠された人間の醜い部分をしっかりと描いた作品です。
原作はなんと日本の作家、遠藤周作の『王妃マリー・アントワネット』
⑥『1789 -バスティーユの恋人たち-』

脚本・監督・音楽
脚本:ダヴ・アチア
演出:小池修一郎
音楽:ロッド・ジャニス 他
あらすじ
舞台は18世紀末フランス。
農夫ロナンは不条理な理由で貴族に父を殺されてしまう。復讐を誓ったロナンはパリへ向かった。
パリでは新しい時代を切り開こうと、ロベスピエール、ダントン、デムーランらの若者たちが熱く革命に燃えていた。そんな彼らの熱い想いに共感したロナンは革命に身を投じることとなった。
そんなある日、王妃マリー・アントワネットの子供たちの教育係であったオランプと出逢い、恋に落ちる。
激動のフランスを生きる恋人たちに、ついに革命の火ぶたが切って落とされる・・・
みどころ
フランス革命ミュージカルのひとつではありますが、特徴としては恋人たちの目線で描かれた革命であるということ。
そのせいもあってか、リアルで残酷なフランス革命・・・というよりは、オシャレで少女漫画チックな作風。
史実通りの血生臭いフランス革命作品を観たい!という人には正直あまりオススメできません。逆に、残酷なのは苦手だけど革命作品が好きだ、という人にはぴったり。
恋人たちがキャッキャウフフ・・・としているうちになんやかんやあって革命が始まるという印象。
特徴としてもうひとつあげられるのは、従来のミュージカルのようなオーケストラによる演奏ではなく、デジタルミュージックであること!
これは最初かなり驚きましたし、違和感も凄かった。でも段々とハマっていくんですよね。
ワシはオーケストラしか認めん!!という頑固おやじタイプにはオススメできません。いい意味でも悪い意味でもグランドミュージカルっぽくない新時代のミュージカル。
好きな人はめちゃくちゃ好き。合わない人はとことん合わない。そんな作品かなと思います。
フランス初演版は日本版の音楽よりもさらにデジタルになっていてカッコいいです!ミュージカルソングとは思えないほどオシャレな楽曲たち。ランニングのお供にも良さそう?
⑦『壁抜け男』(劇団四季)

脚本・監督・音楽
原作:マルセン・エイメ
脚本:ディディエ・ヴァン・コーヴェレール
演出:アラン・サックス
音楽:ミシェル・ルグラン
あらすじ
舞台は20世紀パリ。
郵政省の窓際族として毎日地味に平凡に生きるデュティユル。真面目だけが取り柄の彼の暮らしぶりはなんの派手さもないものでしたが、そんな暮らしも悪くないと気に入っている。
家と職場を行き来するだけの人生に転機が訪れる。なんと”壁をすり抜ける能力”を手に入れたのだ。
パンを盗んでみたり、宝石を盗んでみたり。ありとあらゆる大胆さを見せつけるデュティユル。しかし何をやっても満たされない。
それもそのはず、彼が密かに想いを寄せるイザベルに気づいてもらえないからだ・・・
みどころ
フランスが舞台のミュージカルといえば「革命」「オペラ座」「王族」・・・なんとなく高貴で非日常のイメージがします。
しかし、『壁抜け男』はパリの下町で暮らすなんとも平凡なさえない郵政省の職員が主人公。
そんな男がある日突然、”壁をすり抜ける能力”を手に入れるなんていう、一体なんのこっちゃという感じのストーリー。
ド派手な演出もなければ目を見張るような起承転結があるわけでもない。でもなんだか心がじんわりとするような不思議な作品なんですよね。
超能力を得てしまったけど、やっぱりいままでの普通の生活に戻りたい。だってそれが僕の人生なんだものという、デュティユルが歌う「普通の人間」という曲の中にこんな歌詞があります。
普通の人間 まじめな役人
平凡だけれど 人生はそういうもの
趣味はささやかに 心温かく
派手さはないけど 僕の人生
これこそ究極の人生論だと思います。
色んなミュージカルがあるけれども、ここまで人生についての核心に迫った作品って実はあんまりないんですよね。
歌詞の通り派手さはないけど、ぜひ一度は観て欲しい作品です。
ちなみに、
それにしても『レ・ミゼラブル』のバルジャンといい、『マリー・アントワネット』のマルグリッドといい、『壁抜け男』のデュティユルといい、フランスミュージカルの登場人物はとにかくパン盗みますよね。
通過儀礼かなんかなんでしょうか。もはやお家芸。
と思いきや、実は『壁抜け男』の原作は第二次世界大戦中につくられた作品なので、時代背景である飢えを連想させるためにパンを盗む描写を入れたという作品背景があります。
⑧『ラ・カージュ・オ・フォール』

脚本・監督・音楽
原作:ジャン・ポワレ
脚本:ハーヴェイ・ファイアスタイン
音楽:ジェリー・ハーマン
あらすじ
舞台は南フランスのゲイクラブ「ラ・カージュ・オ・フォール」
オーナーのジョルジュと、看板スターの“ザザ”ことアルバンは20年間同棲し、事実上の夫婦として生活してきた。
ジョルジュには、一度だけ交際した女性との間にできた息子ミッシェルがいて、アルバンが母親代わりとなり育ててきた。
ある日、ミッシェルが突然結婚を宣言した。しかし、よりによって結婚相手はゲイクラブを厳しく取り締まるべきだと主張する政治家の娘だったのだ。
家族揃って挨拶に来ることになったが・・・
みどころ
ミュージカルらしいコメディタッチの展開が楽しめる作品ですが、根底にあるのは家族愛。
ショーとしても楽しめるシーン満載ですが、誰が観てもホロリとくるストーリーがやはり良い。
一見するとドタバタコメディなのですが、誰しもに必ず訪れる現象である老いがひとつのテーマになっています。
ゲイクラブの看板スターであるアルバンは押し寄せる老いに気もふさぎ込みがち。でもメイクをして派手に着飾ればステージの上では一流のショースター。
アルバンが浴びる拍手喝さいの裏にはそんなほろ苦い現実があるんですよね。
今でこそセクシャリティの自由や生き方の多様性が急速に認められつつある世の中ですが、上演当時の30年前であればかなりセンシティブなテーマでした。
家族愛を説くのにわざわざゲイ夫婦が主役である必要があるのか、という声もあったとか。でもそんな批判を跳ね除けるほど、この作品の根底にある人間愛には説得力があります。
普遍的な作品であるからこそ、日本初演の1985年から30年以上も愛され続けれている作品なのだと思います。
さいごに
今回はフランスが舞台のミュージカル8選を紹介しました。
共通する特徴として挙げられるのは、伝記モノや英雄モノよりも家族愛など普遍的なメッセージ性を含んだ作品が多いこと。
今でこそオシャレで優雅なイメージのあるフランスですが、数々の血生臭い革命を乗り越えてきた激動の地ですからね。
その歴史的な背景から、人がどう生きていくかという生き様を描いた作品が多いのかもしれません。
おしまい!











